 |
ٹزŒ³‹@”\‚ًژ‚½‚¹‚½–³—nچـŒ^“ٌ‰tگ«“ءژêƒGƒ|ƒLƒVژ÷ژ‰Œn‚إگشژK‚©‚çچ•ژKپiƒ}ƒOƒlƒ^ƒCƒgپFFe3O4)‚ض“]ٹ· |
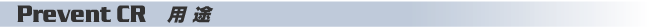 |
پœگخ–ûپAƒKƒXپA‰»ٹwƒvƒ‰ƒ“ƒg“™‚ج”ُ’~ƒ^ƒ“ƒNپE”zٹاگف”ُ‚ب‚ا‚ج“ء‚ة‰–ٹQ‘خ‰‚ة—LŒّ
پœ‘—“d—p“S“ƒ‚┓dڈٹپA‹´—ہ‚ج“S•”پAچHڈêپE‘جˆçٹظ‚ب‚ا‚ج‹à‘®‰®چھ‚ب‚اپA‚ ‚ç‚ن‚é“S•”‚ج–hگH
پœ‹´—ہ‚ج‹´‹r•â‹چ|”آٹھ‚«—§‚ؤچH–@ژ‚ج’چ“ü
پœ‘D”•پAچ`کpژ{گف“™‚ج‰–ٹQ•…گH‚ج–hگH
پœ“S‹طƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒg‚جƒNƒ‰ƒbƒN•âڈC‚ئ“à•”“S‹ط‚ج–hگH |
|
| ’چ“üچـ‚ئ‚µ‚ؤ |
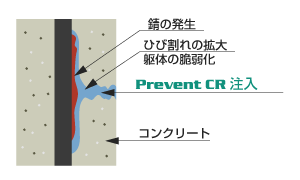
پuPreventCRپv‚ح’ل”S“x‚ب‚½‚ك’چ“ü‚ھ—eˆص‚إ‚ ‚èپAƒNƒ‰ƒbƒN•”پAگعچ‡ٹشŒ„•”‚ب‚ا‚ة—eˆص‚ةگZ“§‚µ‚ـ‚·پB
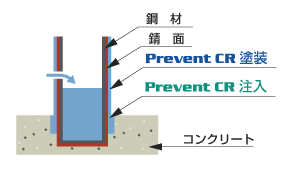
ƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒg‚ج’†گ«‰»‚ة‚و‚èپAڈ]—ˆ•…گH‚µ‚ب‚©‚ء‚½ƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒg’†‚جچ|چق‚à’m‚ç‚ب‚¢‚¤‚؟‚ة•…گH‚ھگiچs‚µپA‚ ‚éژ“ث‘RچھŒ³‚©‚çگـ‚ê‚é‚ئ‚¢‚ء‚½ژ–Œج‚ھ‚¨‚±‚è‚©‚ث‚ـ‚¹‚ٌپB
پuPreventCRپv‚ً“K—p‚·‚éژ–‚إ’n–ت‰؛‚ج–hگHڈˆ—‚ھ‰آ”\‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پBƒpƒCƒvڈَ‚ج“à•”‚ج•…گH‚ة‘خ‚µپA“r’†‚©‚ç’چ“ü‚·‚邱‚ئ‚ة‚و‚èپA–hژKڈˆ—‚ً‚·‚é‚ئ‹¤‚ة•â‹‚à‚©‚ث‚ـ‚·پB
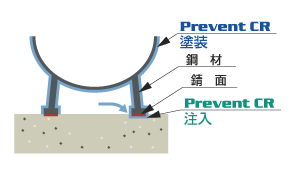
ƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒg“y‘نڈم‚جچ|چ\‘¢•¨‚ج’ê•”‚ة”گ¶‚µ‚½ژK‚àپuPreventCRپv‚ً’چ“ü‚·‚邱‚ئ‚إ–hگHڈˆ—‚ھ‰آ”\‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB
|
| پuPreventCRپv‚ح–³—nچـŒ^“ٌ‰tگ«“ءژêƒGƒ|ƒLƒVژ÷ژ‰Œn’چ“üچـ‚ئ‚µ‚ؤپAƒGƒ|ƒLƒVژ÷ژ‰‚ج“ء’¥‚إ‚ ‚é•t’…گ«پA‘د–ٍ•iگ«پA‘دگ…گ«پA‘د‰–گ…گ«‚ة—D‚ê‚ؤ‚¢‚éژ÷ژ‰‘w‚ئپAچX‚ةچ|چق‚جژK‘w‚ةگZ“§‚µ‚ؤژK•”‚ًچ•ژKپi‰بٹw“I‚ةˆہ’肵‚ؤ‚¢‚éƒ}ƒOƒlƒ^ƒCƒgپj‚ة•دٹ·‚³‚¹‚é‹@”\‚ًŒ“‚ث”ُ‚¦‚ؤ‚¨‚èپAڈ]—ˆ‚ج’چ“ü•û–@‚إپA“à•”“S‹ط‚ج–hژKڈˆ—‚à“¯ژ‚ةچs‚¢پAژK‚ة‚و‚é“S‹ط‚ج–c‚ê‚ًژ~‚ك‚ؤپAƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒg‚ج”ڑ—ô‚ً–h‚®–ًٹ„‚ً‰ت‚½‚·‚±‚ئ‚ھ‰آ”\‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB |
| ƒvƒ‰ƒCƒ}پ[‚ئ‚µ‚ؤ |
گشژK‚ھ”گ¶‚·‚é‚ئچ|چق‚ح•…گH‚µ‚ـ‚·پB‚»‚ج‚½‚ك–hژKچـ‚ً“h•z‚µ‚ـ‚·‚ھڈ]—ˆ‚ج“h—؟‚إ‚حژdڈم“h‘•‚ةژٹ‚é‚ـ‚إ‚ةژèٹش‚ئ“ْگ”‚ھ•K—v‚ئ‚µ‚ـ‚µ‚½پB
‚µ‚©‚µپAپuPreventCRپv‚حگشژK‚ةگZ“§‚µپAچ•ژK‚ج”–‚¢”ç–Œ‚ًŒ`گ¬‚µپAƒGƒ|ƒLƒVژ÷ژ‰‚إŒإ‚ك‚éˆêکA‚جچى‹ئ‚ة‚و‚èپAژK‚رژ~‚ك‚©‚ç’†“h‚è–ک‚ًٹ®—¹‚·‚邱‚ئ‚ھ‰آ”\‚إ‚·پB
‚ـ‚½پAپuPreventCRپv‚حژ¼ڈپڈَ‘ش‚جژK–ت‚إ‚à•‚‚«ژK‚ًڈœ‹ژ‚µ‚ؤ‚»‚ج‚ـ‚ـ“h•z‚·‚邱‚ئ‚ھ‰آ”\‚إ‚·پB |
|
|
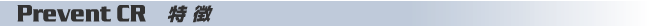 |
پœچى‹ئٹآ‹«ˆہ‘Sگ«
‰”پAƒNƒچƒ€“™‚جڈd‹à‘®‚حٹـ‚ٌ‚إ‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB
–³—nچـŒ^‚إ‚·پBƒLƒVƒŒƒ“پAƒgƒ‹ƒGƒ““™‚ج—L‹@—nچـ‚حٹـ‚ٌ‚إ‚¨‚è‚ـ‚¹‚ٌپB
ژKژو‚èچى‹ئ‚جٹب‘f‰»‚ة‚و‚蕲گo‚ج”ٍژU‚ً‘ه•‚ةŒ¸ڈ‚µ‚ـ‚·پB
پœگع’…—ح‚ئ–hژK—ح‚ھ—اچD
ƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒg‹ë‘ج“¯ژm‚جˆê‘ج‰»پAچ|ژK–ت‚ئ‚جگع’…—ح‚ئ–hژKگ«‚جŒüڈم‚ً”ٹِ‚µ‚ـ‚·پB
پiژK–تˆّ’£گع’…‹“xپ@‚R‚SپD‚RKgfپ^‚ƒ‡uپj
پœ–³پ@ژûپ@ڈk
—nچـ“™‚جٹِ”•¨‚حٹـ‚ـ‚ê‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ج‚إچd‰»ژ‚جژûڈk‚ب‚ا‚ج‚₹‚ًگ¶‚¶‚ـ‚¹‚ٌپB
پœژK“]ٹ·‹@”\‚ً•t—^
چ|‚جژK‘w‚ة—eˆص‚ةگZ“§‚µپAژK–ت‚ً‰بٹw“I‚ةˆہ’肵‚½ƒ}ƒOƒlƒ^ƒCƒgپiFe3O4)ni“]ٹ·‚·‚é‹@”\‚ًژ‚½‚¹‚邱‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤڈ]—ˆ‚جژKژ~‚ك“h—؟‚ة”ن‚ׂؤ–hگHگ«”\‚ھ‘ه•‚ةŒüڈم‚µ‚ـ‚µ‚½پB
پœ‘د‹vگ«
چd‰»Œم‚ج‘دگ…پA‘د‹vپA‘د–ٍ•iگ«‚ة—D‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پœ‘f’n’²گ®‚ھٹب’P‚إ•t’…گ«‚ئ–hژKگ«‚ھ—اچD
ٹب’P‚ب‚RژيƒPƒŒƒ“’ِ“xپi‘S–ت‚ةچH‹ï‚ً‚ ‚ؤپA—ٍ‰»“h–Œ‚ًڈœ‹ژ‚µپA“S‘f’n–ت‚ج•‚‚«ژK‚حƒڈƒCƒ„پ[ƒuƒ‰ƒV‚إڈœ‹ژ‚·‚é’ِ“x‚ئ‚µپA–û•ھ‹y‚ر‚ظ‚±‚è‚حڈ[•ھڈœ‹ژ‚·‚éپj‚إ•t’…گ«‚ئ–hژKگ«‚ً”ٹِ‚·‚éƒGƒ|ƒLƒVژ÷ژ‰“h–Œ‚ًŒ`گ¬‚µ‚ـ‚·پB
پœ‹Œ“h–Œ‚ئ‚جƒٹƒtƒeƒBƒ“ƒOŒ»ڈغپi‘f’n‚ئ‹Œ“h–Œٹش‚ج”چ—£پj‚ھ‹N‚±‚è‚ـ‚¹‚ٌپB
’تڈي‚ج“h—؟‚حچى‹ئگ«‚ً—ا‚‚·‚邽‚كپAژ÷ژ‰‚ج—n‰ًگ«‚ھ‹‚¢—nچـ‚ً‘½—ت‚ةٹـ‚ٌ‚إ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚ج‚½‚ك“h–Œچd‰»”½‰ژ‚ة‚ح—nچـ‚ھڈِ”پAڈƒ“h–Œ•ھ‚جژûڈk‚ً‹N‚±‚µپA‹Œ“h–Œ‚ً—n‰ً‚µ‚â‚·‚¢“™‚جŒ´ˆِ‚إ‹Œ“h–Œ‚ئ‚جƒٹƒtƒeƒBƒ“ƒOŒ»ڈغ‚ھ‹N‚«‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پBپuƒvƒٹƒxƒ“ƒgCRپv‚حƒٹƒtƒeƒBƒ“ƒOŒ»ڈغ‚ھ‹N‚±‚è‚ـ‚¹‚ٌپB
پœ“h‘•چH’ِ‚جچ‡—‰»
ڈ]—ˆ‚جڈd–hگH“h‘•‚إ‚ج•âڈCچHژ–‚ة‚¨‚¢‚ؤپAچى‹ئ‚جچH’ِپEچHٹْ‚ج’Zڈk‚ھ‰آ”\‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB
| ƒvƒٹƒxƒ“ƒgچH–@ |
ڈ]—ˆژK‚رژ~‚كچH–@ |
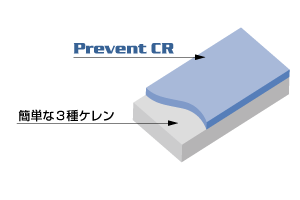 |
![ڈ]—ˆژK‚رژ~‚كچH–@](images/cera/conventional-method.gif) |
|
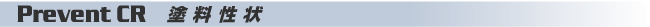 |
| |
ƒvƒٹƒxƒ“ƒgCR
پi‰ؤ‹G—pپj |
ƒvƒٹƒxƒ“ƒgCR
پi“~‹G—pپj |
| ژه گ¬ •ھ |
ژهچـ |
چd‰»چـ |
ژهچـ |
چd‰»چـ |
ƒGƒ|ƒLƒVژ÷ژ‰ |
•دگ«ژ‰ٹآژ®ƒ|ƒٹƒAƒ~ƒ“
ƒ|ƒٹƒ`ƒIپ[ƒ‹ |
ƒGƒ|ƒLƒVژ÷ژ‰ |
•دگ«ژ‰–b‘°ƒ|ƒٹƒAƒ~ƒ“
ƒ|ƒٹƒ`ƒIپ[ƒ‹ |
چ¬چ‡”ن—¦
پiڈd—ت”نپj |
ژهچـپFچd‰»چـپپ‚QپF‚P |
| گFپ@پ@‘ٹ |
ƒNƒٹƒ„پ[ |
| ”نپ@پ@ڈd |
1.20پ}0.10 |
”Sپ@پ@“x
[mPaپEs] |
2000پ}1000 |
چd‰»ژٹش
پiژwگGٹ£‘‡پj |
‚Q‚Sژٹش
|
| ‰آژgژٹش |
‚T‚O•ھ |
| —eپ@پ@—ت |
6‚‹‚‡ƒZƒbƒgپiژهچـ ‚SkgپAچd‰»چـ ‚Qkg پj
|
|
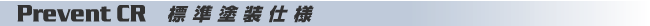 |
| چHپ@پ@’ِ |
ڈˆ—‚ـ‚½‚ح“h—؟–¼ |
•Wڈ€“h•z—ت
[g/‡u] |
•Wڈ€–‹Œْ
[ƒتm] |
“h‘•ٹشٹu
پi20پژپj |
| ‘f’n’²گ® |
•‚‚«ژK‚â—ٍ‰»“h–‹‚حڈœ‹ژپi‚RژيƒPƒŒƒ“پj
–û•ھ‚â‚ظ‚±‚è‚حڈ\•ھڈœ‹ژ
|
| ‰؛پ@پ@“h |
ƒvƒٹƒxƒ“ƒgCR |
‚P‚Q‚O |
‚P‚P‚V |
‚Q‚Sژٹش
پ`‚V“ْ |
| ڈمپ@پ@“h |
ڈم“h‚è“h‘•پiژg—p–ع“I‚ة‚و‚è‘I’èپj |
|
|
|
|
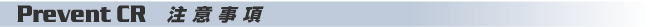 |
‚PپDچ¬چ‡‹y‚رکa‚ة‚آ‚¢‚ؤ
- ڈd—ت‚إژهچـپi‚Qپj‚ة‘خ‚µچd‰»چـپi‚Pپj‚جٹ„چ‡‚إ‘¬‚â‚©‚ةچ¬چ‡‚µپAڈ[•ھ‚ةکa‚ً‚µ‚ؤ‚©‚炲ژg—p‚‚¾‚³‚¢پB
- ‹C‰·‚Q‚Oپژˆبڈم‚إچى‹ئ‚ً‚³‚ê‚éڈêچ‡‚حپAژ÷ژ‰‚ج‰·“x‚ھˆظڈي‚ةڈم‚ھ‚èپA‹}Œƒ‚ةچd‰»‚ً‚·‚éڈêچ‡‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ج‚إڈ\•ھ’چˆس‚ً‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB‰·“x‚جڈمڈ¸‚ً”ً‚¯‚é‚ة‚حŒû‚جچL‚¢گَ‚¢—eٹي‚ةˆع‚µ‚ؤ‚²ژg—p‚‚¾‚³‚¢پB‚ـ‚½پAڈ—ت‚¸‚آ‚ـ‚؛‚ؤ—lژq‚ًŒ©‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
‚QپDژg—p‚ة‚آ‚¢‚ؤ
- ‘f’n’²گ®‚حپA“h‘•–ت‚ج•‚‚«ژKپA—ٍ‰»“h–‹‚جڈœ‹ژپi‚RژيƒPƒŒƒ“پjپA–û•ھ‹y‚ر‚ظ‚±‚è‚حڈ\•ھ‚ةڈœ‹ژ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
- “h–ŒŒْ‚ح‚P‚O‚Oپ`‚P‚Q‚Oƒتm‚ًٹm•غ‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
- چd‰»‘O‚ة‰J‚âپAگ…‚ھ‚©‚©‚ç‚ب‚¢‚و‚¤‚ة—{گ¶‚ً‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
- ‹C‰·‚ھ‚Tپژˆب‰؛‚إ‚ج‚²ژg—p‚ح‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپB
- ژg—p‚ةچغ‚µ‚ؤ—nچـ‚ة‚و‚éٹَژك‚حچs‚ي‚ب‚¢‚إ‰؛‚³‚¢پB
‚RپD•غٹا‹y‚رژو‚舵‚¢‚ة‚آ‚¢‚ؤ
- ژهچـپAچd‰»چـ‚ئ‚à“ْ‰A‚ج—ء‚µ‚¢ڈêڈٹ‚ة•غٹا‚µ‚ؤ‰؛‚³‚¢پB
- ژو‚舵‚¢‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپAپuƒGƒ|ƒLƒVژ÷ژ‰“h—؟‚جژg—pڈم‚ج’چˆسژ–چ€پv“™‚ًژQچl‚ة‚µ‚ؤپAˆہ‘SپA‰qگ¶“™‚ةڈ\•ھ’چˆس‚ً‚µ‚ؤژو‚舵‚¢‚‚¾‚³‚¢
|
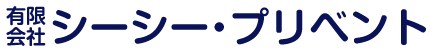

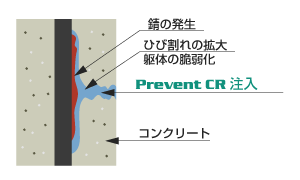
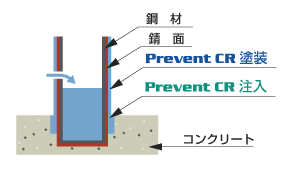
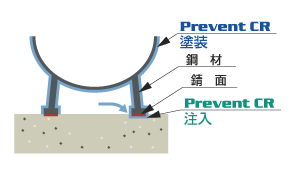
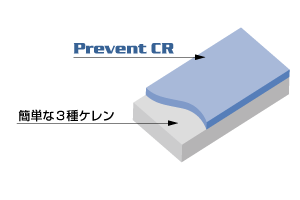
![ڈ]—ˆژK‚رژ~‚كچH–@](images/cera/conventional-method.gif)